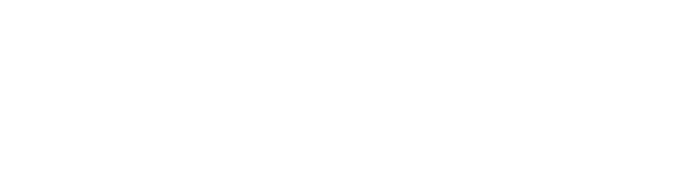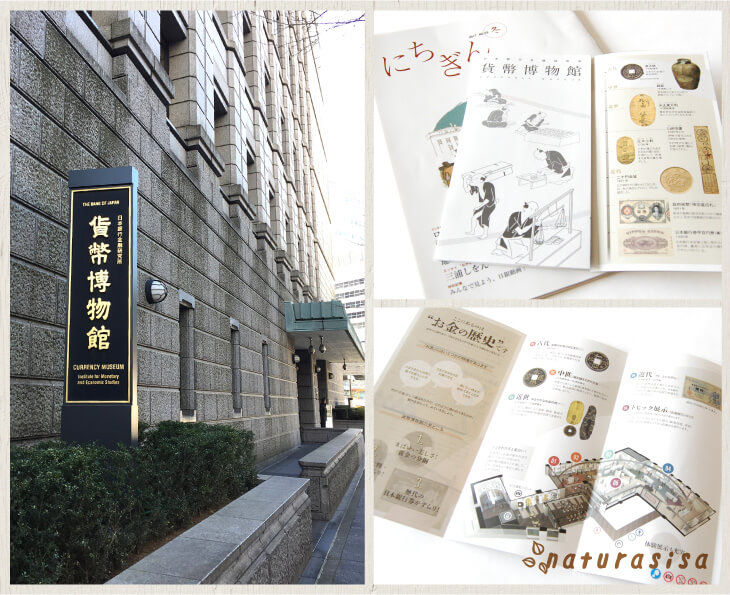この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
飯田橋にある『東京大神宮』に初詣に行ってきました♫
毎年東京大神宮に参拝に行きますが、今回は混雑を避けて早朝に伺いました。
東京大神宮の早朝の雰囲気や混雑具合、参拝の作法をご紹介します。
東京大神宮|早朝の参拝

朝8時過ぎに最寄り駅の『飯田橋駅』から出発。
ところどころに東京大神宮への看板があるので迷わずに向かえると思います。
今回は早朝で人がまばらですが、日中なら東京大神宮へ向かう人の流れができています。
さて、到着した時刻は8:10分ほど。
参拝者が少なく、手水舎まで待つことなく進めました。
おかげで心も落ち着いて、手水の作法ができました。
東京大神宮では、手水を済んだ方ひとりひとりに、巫女さんが手水紙を渡してくれます。
頂いた手水紙で手を拭いて、門をくぐります。
この儀式だけでも少し清められた気分になります。
朝の冷たい澄んだ空気と静かな境内でリラックス。
まず先にお正月飾りを収め(手前に古札納所があります)、神殿までの石畳の道を静かに進みます。
神殿前にある参拝作法に従い、ゆっくり参拝することができました。
参拝のあとは、恒例のおみくじを。
おみくじは恋愛と生活の2種類あり、生活全般は100円、恋みくじ200円。
縁結びにゆかりの深い神社なので、恋みくじが圧倒的に人気です。
早朝の参拝は凛とした空気で、清々しい気分になりますよ。早起きが得意な方はぜひ。
東京大神宮|夜の参拝
去年は、16時ごろ(3連休の間)に初詣に行きましたが・・東京大神宮までの道のりに長蛇の列が!
道をまたいで近くの駐車場までなが〜い列が続いていました。
警備員さんも「1時間以上待ち」と伝えていたので、諦めて近くで食事をすることに・・。
食事を終えてから改めて見に行くと、入り口付近だけの短い列になっていました!
18時30分過ぎの閉館前だったからだと思います。
夜の東京大神宮の雰囲気も厳かでステキでした。
休日で静かに初詣するなら、早朝か夜(閉館前)が落ち着いて参拝できると思います。
追記 2020年の参拝は、3連休の17時頃に到着。
混雑具合は神宮の出口付近までの列、参拝まで約30分並びました。
東京大神宮|お参りの仕方
二拝 二拍手 一拝
お参りの作法は、神社に参拝するときと同じく、心を込めてお祈りしましょう。
手水の作法
昨年と今年は柄杓がなく、細い木の筒が5つほど横に並び、そこから水が流れていました。
大勢の参拝客のために改良したのかもしれませんが、とても衛生的でいいですね。
拝礼の作法
二拍手のあと、両手の指先を揃えて祈りをこめます。
ご祈祷のときも、玉串を捧げて「二拝二拍手一拝」の作法でお参りします。
参道で並んでいる間に予習しておくと間違いなし!
幸多き年となりますように!!!